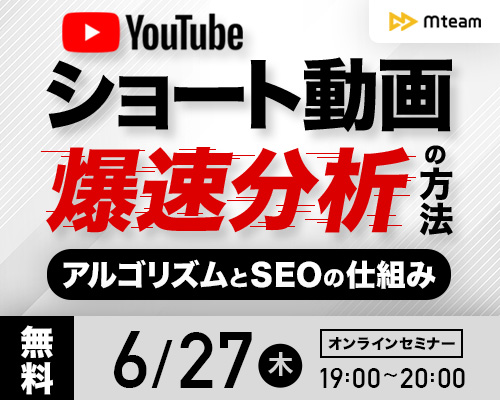コラム

動画マーケティングに最適なKPIの設定方法とは?
今回は、動画マーケティングとKPIの関係について紹介しますので参考にしてみてください。
目次
動画マーケティングのKPI設定してる?

まず、動画マーケティングにおいて成功するためにはKPIがどのようなものか知る必要があります。KPI(キー・パフォーマンス・インジケーター)は日本語で重要業績評価指標です。簡単に言うとマーケティングにおいて「効果を測定」するためのもの。効果を可視化し改善を加えていくために必要な数字であり、動画マーケティングにおけるKPIは評価指標を達成するための「中間目標」の扱いとなります。
動画広告を出す際には、動画自体の目標が達成されているかを段階的に測定する必要があるため、測定したデータをもとに修正をかけていくということできるようになります。動画制作をおこなう時点でKPIを設定しておくことが、動画マーケティング成功のカギを握っているのです。設定していない状態で、動画マーケティングをおこなうことも可能ですが、途中でどこに向かっているのかわからなくなり、視聴者の反応も知ることができないため、動画制作に行き詰ってしまう可能性が高くなってしまいます。個人、企業を問わず動画マーケティングをおこなう場合には、KPIを意識した動画制作が求められているということを覚えておきましょう。
動画マーケティングにKPI設定が必要な理由

KPI設定が必要な理由は、会社の名前、商品やブランドを動画で宣伝したい際には、動画の視聴者がどのぐらい興味を持っているのか、視聴者との距離感を測るためです。「どこに向かっているのか分からない」というような先行き不安な状態を作ってしまうことがないように道筋を作ってくれるのがKPIです。設定しておくことによって、修正を加えながら正しい方向に進むことができるので、動画マーケティングでは動画の制作と同じレベルでKPIは重要と言えます。
KPIを設定するメリット
- 目標が明確になるのでやらなければいけないことが分かる
- 動画制作における弱点が分かるので克服しながら進めることができる
- 動画制作チーム単位で1つの目標に向かうことができる
- 必要な費用、組まなければいけないスケジュールが見えてくる
- KPIをクリアしていくことによって得られる達成感や成長が実感できる
動画マーケティングのKPIの例
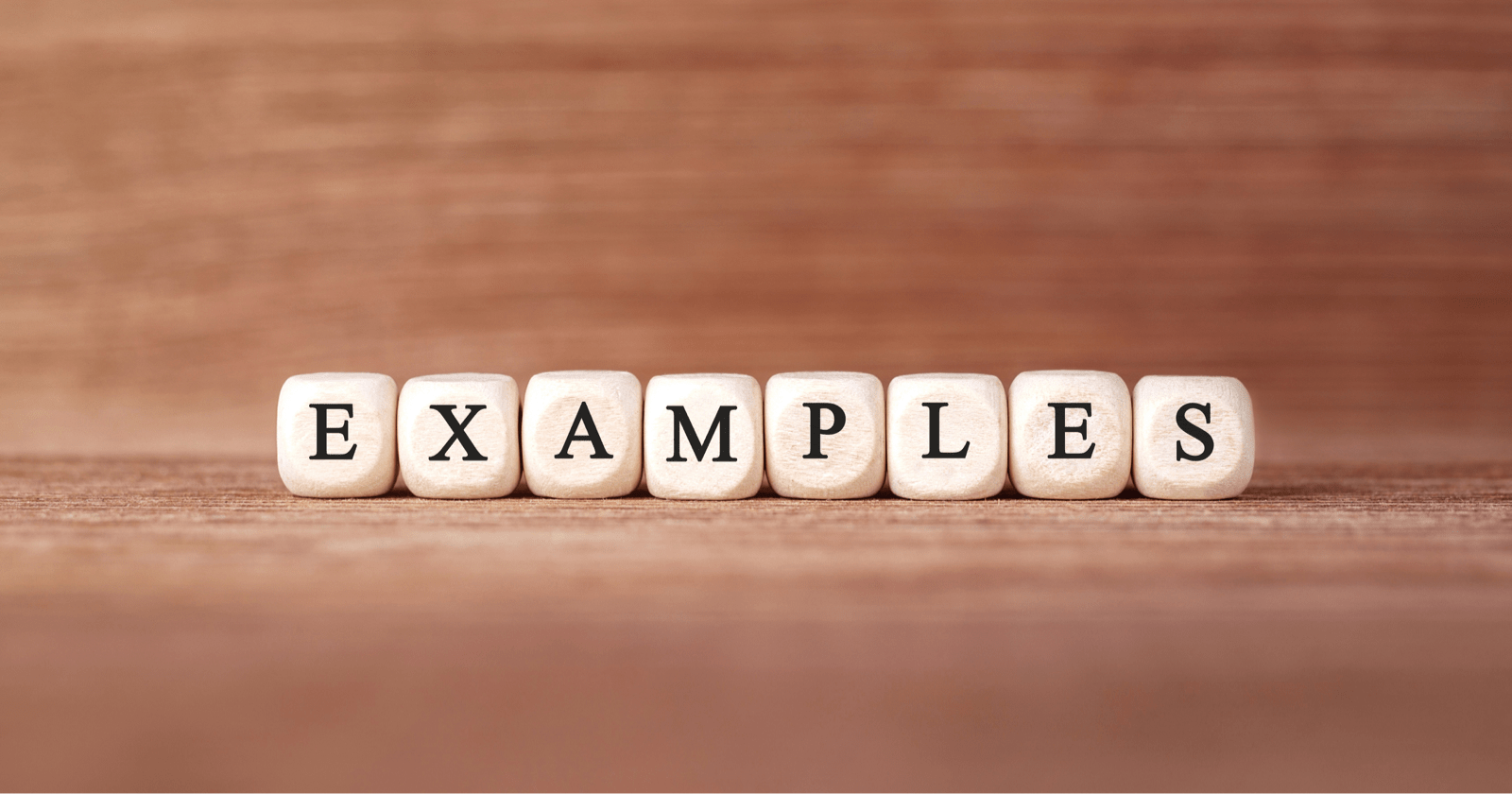
まず、KPIは業態や職種によって形が異なるということを知っておきましょう。
例えば、保険の営業の職種であれば「訪問件数」「アポイント件数」「成約率」といったデータ、システム開発の職種であれば「レポート件数」「エラー数」といった具合に、参考にしなければいけないデータは全く違うものになっています。今回のテーマである動画マーケティングで必要な部分についてはいくつかありますので、以下のデータは最低限押さえておきましょう。
動画マーケティングで必要なデータ
- 視聴完了率 – 動画が30秒以上再生された、または完了まで再生された回数
- 再生時間 – 動画の総再生時間
- クリック数 – 動画内の広告がクリックされた回数
- コンバージョン率 – 動画を通じて商品やブランド、サービスが購入された率
- インプレッション数 – 動画内の広告が表示された回数
動画マーケティングにおけるKPIは、例えば「前週比10%の視聴完了率を増やす」、「前月比クリック数20%を増やす」などといったものが具体的な指標となります。数字はあくまでも目標に向かっていくためのものとなるので、動画制作チームで話し合いを持ち、現実的に達成できる範囲を設定し1つずつクリアしていくのが理想です。業態、業種によってKPI設定の際に見なければいけない項目や数字は異なってきますので、動画マーケティングではこの数字に着目すればいいという感覚をまずは身に着けることが、KPIを設定する上では大切です。
動画マーケティングのKPI設定手順

KPIの設定手順としては、最終的なゴールを設定するところから始めます。動画マーケティングでは【目的と数値を決める】、【期間を決める】といった2つを具体的に設定していくところから始めます。これらを具体的にすることによって、動画の方向性とKPIを決めることができます。
目的と数値を決める
どういった目的で動画マーケティングをおこなうかは、商品やサービスによって1つ1つ異なりますが、一般的な内容としては商品やサービスの「認知」、「販売」をゴールにするケースが大半です。
認知をゴールにする
消費者に商品やブランドを知ってもらうという場合のKPIの設定の仕方としては、「視聴回数」や「インプレッション数」に注目していきます。具体的には、1つの動画に対して視聴回数10万回、インプレッション数3万回など各項目に目標とする数字をつけていく形となります。どれだけの回数動画を見られているのかを把握し、そのデータをもとに他の動画と比較します。リアルタイムで出てくる数字をもとに、次回以降の動画マーケティングに生かすという流れです。
まずは動画を再生してもらわなければいけませんので、動画のタイトルや動画の内容が視聴者にとって魅力的に映らなければいけません。こんな商品、サービスがありますということを視聴者に知ってもらうための動画に仕上げる必要があります。動画内で視聴者の視覚や聴覚をくすぐるキャッチフレーズや覚えやすいロゴを作成するなどといった、動画コンテンツとしての工夫も必要となってきます。
販売をゴールにする
消費者に商品やブランドを購入してもらうためには「クリック数」、「コンバージョン率」に注目します。具体的には、1つの動画に対してクリック数1万回、コンバージョン率5%など数字を設定していくことになります。特に、クリック数が低い場合、動画内のコンテンツが消費者を惹きつけることができていないという根拠にもなりますので、動画の構成など根本的な見直しや方向転換の必要性も出てきます。商品やブランドを知ってもらうだけでなく、広告からクリックして進み購入してもらうという複数の工程が必要になりますので、視聴者の心を動かす動画にする必要があります。動画の内容やコンテンツの充実度、完成度が求められますので、少しハードルが高くなってきます。
視聴者の興味を惹き、商品やブランドの良さを伝える動画内容にしなければいけませんが、あまりにも長すぎる動画や、説明が具体的すぎると視聴者が離れてしまうという傾向がありますので、具体的な動画にしすぎるというのも注意が必要です。短時間で視聴者に強いインパクトを与えられるような動画を作るといった工夫も必要となってきます。
期間を決める
目的と数値が決まったら、最後に達成するための期間を設定していきます。KPIの効果を測定するためにはある程度期間を区切って見ていく必要があるためです。具体的には「1週間」「1か月」といった単位で測定していき、数字が達成されているのかどうかを判断し、既存動画への改善、新規動画への落とし込みなど、測定したデータを活用して、施行を試していきます。
できれば短いスパンで期間を設定していくことが理想ですが、人員が割けずに稼働が取れない場合は最低でも1か月単位で見ていくスタンスでも問題ありません。期間を決めるというシンプルなものですが、アップロードした動画が正しく出せていたのか「答え合わせ」になるためしっかりと定期的に続けることが大切になってきます。
動画マーケティングのKPIを測定に便利なツール

KPIの測定にはツールを使うのが効率的です。ここでは、動画マーケティングのKPI測定に使えるツールを紹介します。
ムビパス
ムビパスの良さは動画の測定が非常に簡単という点です。管理画面から動画をアップロードしてURLを発行するだけの操作なので、事前の準備も特に不要でスピード感のある測定が可能です。個人レベルでの測定ができるので、何秒間その動画を見てくれているのか、最後まで動画を見てくれているのかを把握できます。特に新商品や新しく発表するブランドは個人レベルでの地道な測定も必要となってきますので、細かい測定をしたい際におすすめのツールです。これまでの集団的な効果測定ではなく、ターゲットを1人に絞った個人レベルで測定することでより正確なデータを出せるため、商品の購買、ブランドの成約率アップにも期待できます。
個人レベルで測定できるので深いところまでデータを取りたい場面で活躍しますが、操作性も簡単なため初心者向きとも言えるツールです。現在はまだベータ版が限定配信されている段階ですが、興味がある方は運営会社に問い合わせてみましょう。
PlayAds
「クリエイティブは検証してから作る時代に」というコンセプトを持っているのがPlayAdsです。1秒単位で効果を測定できるだけでなく、動画ごとに比較もできるので、これまでアップロードした動画の特性や視聴者の関心を測ることができます。細かく測定することによって、動画の制作の方向性を明確にでき、あいまいな方向に進むことを避けることができます。大企業やベンチャー企業など様々な規模の企業で利用されているツールですが、個人単位で無料プランを利用することも可能となっています。
「動画制作のリソースが確保できない」「配信後の動画の改善点がわからない」「視聴者との距離感がつかめない」といった悩みを可視化できるので、初めて動画を測定するといった方にもおすすめのツールです。
ADPLAN
国内最大級の測定ツールとして知られているのがADPLANです。累計1500社以上がこのツールを導入しているという実績があります。動画マーケティングとして動画自体の計測に限らず、1本あたりの費用対効果も可視化できます。動画ごとのパフォーマンスをダッシュボードにて計測できることに加え、動画に絡んでくる複数の広告もクロス集計分析により短時間でデータ化できることも強みです。
いつ、どこで、どんな人が見ているのかその日の天気まですぐに知ることができますので、徹底した動画分析が可能。ユーザーインターフェースにもこだわっており、ダッシュボードでは各種レポートをワンクリックで閲覧できるので、データの集計の作業効率も最大化されています。動画マーケティングの効果測定をはじめておこなう企業の担当者におすすめのツールです。
Vidyard
「視聴者を顧客に変える」というコンセプトを持っているのがVidyardです。動画分析ツールとして、リアルタイムでインサイトを計測したり、視聴者の詳細を特定できるツールとなっています。どのような状況で動画が再生されているかを把握することによって、商品やブランドの広告を出すのに参考にしたりできます。特にIT系の商品やブランドである場合、広告の出し方や時期が販売に直結しますので、視聴者の状況は重要なデータとなります。視聴者の傾向を知り、より深い分析をすることで、動画の内容を視聴者の好みに近づけることができます。
まとめ

動画マーケティングとKPIの関係性について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。動画マーケティングの効果を測るためのKPIを設定することによって、やらなければいけないことを明確にできます。
商品やブランドの認知を目的にするのか、販売を目的にするのか、最終的なゴールによって動画制作チーム単位で決定していくのがベストです。チーム単位で目標に向かうことができ、達成感を得ることができるだけでなく個人の成長にも期待できるものになってきますので、動画の内容と同レベルで力を入れてKPIを設定していきましょう。
具体的には【目的と数値を決める】、【期間を決める】という2つをできる限り具体的な数字を出して進めることが大切です。明確な目標と正確な数字を出すことによって達成度が出され、動画制作のモチベーションにもつながってくるものですので、KPIの設定は漏れの内容におこないましょう。KPIは適切な動画マーケティングができているかの「答え合わせ」の役割を果たしてくれるものですので、定期的に続けることを意識して取り組んでいきましょう。
WEBでのお問い合わせはこちら