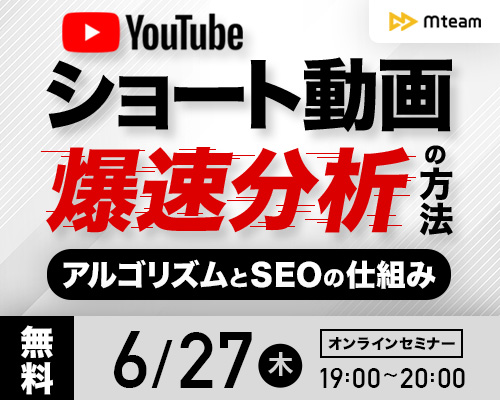コラム

近未来の広告体験!VR広告について紹介
- VRとはどのようなものか
- VR広告と事例
- VRの今後
目次
VRとはそもそも何か

まずVRとは何かご紹介します。
VRの正式名称は「Virtual reality」と呼ばれ、日本語では「仮想現実」と訳されます。 ヘッドマウントディスプレー(HMD)と呼ばれるゴーグル型デバイスを使用することで、コンピューター上で作られた世界を現実世界のように体感できることが特徴です。例えば海外の有名な観光地に本当に行ったかのような体験をすることができ、また、賃貸を検討している際に、実際に部屋を訪れたような体験をすることができます。
また、VRは「CGタイプ」と呼ばれるものと「映像タイプ」と呼ばれるものの2種類が存在します。CGタイプでは、SFなどに代表されるGCで作られた非現実的な空間をリアルに体感することができます。一方映像タイプでは、実際の人物や風景を撮影し、360度全方位を自由な視点で体験することが可能です。
VRは、近年非常に注目されている技術の1つで、今後は日常生活からビジネス活用まで、幅広いジャンルで活用が期待されています。
VR広告とは

YouTubeなどの動画プラットフォームを閲覧すると、閲覧中に広告が表示されることがあります。VRプラットフォームでも同様に、VR空間上に広告を表示させることができます。このVR空間で表示させる広告をVR広告と言います。現在様々な企業がVRを使った広告に取り組んでおり、VRの普及に伴い、新しい広告として定着していくでしょう。
VR広告の最大のメリットは、ユーザーにとってよりリアリティのある体験を提供できることです。現在の広告は主に、テレビ、ウェブサイト、スマホアプリ、YouTubeなどの動画サイトへの出稿が主流となっています。広告の出稿内容は様々ですが、その多くはタレントや、キャッチーなフレーズ、印象付ける演出を、静止画または動画上で表現し、ユーザーの興味・関心を惹きつけるというものです。しかしVR広告では、VR空間でよりリアリティのある体験をユーザーに提供することができます。
例えば海外旅行の広告では、実際にユーザーが検討している旅行先の広告を配信することで、より現地の魅力を疑似体験することができます。また、自動車販売のプロモーションを行う場合、自動車の外観をよりリアルに見ることができ、また車内に乗車して運転席からみる景色を擬似体験することができるでしょう。
このようにVR広告は、ユーザーにとってよりリアルな体験や感動を提供することが可能です。
VR広告の活用事例を紹介

VR技術が注目を集める中、すでにVR広告を実際に活用し、プロモーションを行なっている企業もあります。自社の製品広告から、非常にユニークな使い方まで、その用途は様々です。ここでは、国内・海外でのVR広告の活用事例を3つご紹介します。
MITEKURE
不動産業界は積極的にVRでのプロモーションを取り入れる企業が増加しており、現地に足を運ばずに内見する体験ができるなど、徐々にビジネス活用が浸透しています。そんな中、株式会社リニューアルストアはVRを活用し、不動産VR広告サービス、「MITEKURE」というサービスをリリースしました。
MITEKUREは、賃貸物件をリアルに体験してもらえることはもちろんのこと、中古物件のリフォーム後の世界を体験することができます。これまで不動産会社によるリフォーム予定の中古不動産は、リフォーム内容が明確でないまま販売し、購入判断を迫られていました。しかし、MITEKUREを活用することで、VRで購入前にリフォーム後の物件を内見体験することができ、リフォーム後の内容に納得した上で購入してもらうことが可能となりました。
トヨタ
日本国内の自動車メーカー大手の「トヨタ」もVR広告に注目している企業の1つです。トヨタはVRを活用し、先進安全技術を体験できるVRシミュレーターを導入しました。このVRシミュレーターには車の座席やハンドル、アクセルなどが設置されており、シートとVR映像を連動させることで、カーブでのシートの傾きや、ブレーキをかけた際の衝撃をリアルに再現しています。トヨタはこのVRのプロモーションで、利用者の安全性を配慮した技術を2つ紹介しています。
1つ目の技術は「自動ブレーキ機能」です。 前方車両との距離を自動車が自動的に検知し、衝突の可能性が見込まれた場合、運転手にブザーなどで通知します。また、万が一ブレーキを踏み損ねて衝突しそうになった場合、自動でブレーキがかかり、衝突を回避、または衝突時の被害を軽減してくれます。
2つ目の技術は「踏み間違いサポート機能」です。例えば、駐車場で駐車をする際に、ブレーキとアクセルを踏み間違えてしまい、事故が発生することがあります。このような場面でサポートしてくれるのが、この踏み間違えサポート技術です。低速走行時に万が一踏み間違えてもスピードが出ないように、エンジン出力を抑制します。また、万が一踏み間違えて衝突しそうになった場合は、自動でブレーキをかけて衝突を回避、または衝突時の被害を軽減してくれます。
これまでは、これらの利用者の安全性を配慮した技術は、映像などを通して伝えることはできましたが、実際にその身を持って体験してもらうことは困難でした。しかし、VRを利用することで、実際に事故が起こりそうになるシーンを再現し、その技術と安全性を体感していただくことが可能となりました。VRは、危機体験を再現することで、利用者の安全性という、とても大切な情報を伝える場面でも活用されています。
Davos Klosters
スイスのチューリッヒにある、スキーリゾートのDavos Klostersが行ったプロモーションです。
体験型広告の一環としてVRを街中に設置して、スキーリゾートを体感してもらうプロモーションを実施しました。ブースにはリフトが用意されており、リフトに着席したらVRヘッドセットを装着。そうすると、目の前には本当にスキーリゾートにいるかのような、リアルな雪景色が広がります。そしてそのスキーリゾートで隣にいるのは、なんと「前ミススイス」。VRを活用して、前ミススイスとスキーリゾートでのデート体験が楽しめます。
また、映像内では料理が目の前を通るシーンが用意されており、そのシーンを迎えると、現実世界でも実際にスタッフが料理を持って目の前を通り過ぎて行きます。これにより、よりリアリティ溢れる体験をすることができます。VR体験は、最後に前ミススイスからドリンクを受け取って終了。そしてヘッドセットを外すと、目の前にはまさかのサプライズで本物の前ミススイスが登場します。
VRでの広告と現実世界を組み合わせた、まさに仮想現実な体験が楽しめる活用施策です。
VR広告プラットフォーム
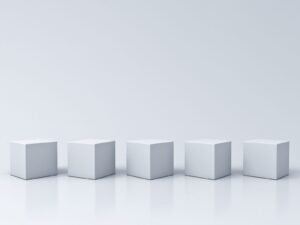
VR技術の発展に伴い、今後より一層VR広告のニーズも高まることが予想されます。それに伴い、スタートアップ企業から大企業まで、VR広告プラットフォームとしての事業を確立するためにサービスの展開を進めています。ここでは数あるVR広告のプラットフォーム企業から3社をご紹介します。
cluster
clusterは、誰もが自宅でエンターテイメントを楽しめるVRプラットフォームです。「徒歩0分のバーチャルイベント会場」というキャッチフレーズのもと、VR空間で、ライブやカンファレンスなどのイベントに参加することができます。また、clusterは利用者により素晴らしいVR体験を提供するために、VRプラットフォームとしてのサービス拡充を進めています。
例えば、2019年6月には「アーカイブ機能」を実装しました。これにより、過去に開催されたVRイベントを何度でも楽しむことが可能となりました。そのほかにも、VRイベントに参加するだけではなく、誰もが主催者になれるように、「会場アップロード機能」を一般公開しました。会場アップロード機能を一般公開することで、clusterのVRプラットフォームを利用し、誰でも簡単にVR空間でのイベントを主催することができるようになったのです。
また、運営元のクラスターはcluster上で過去3回のカンファレンスを開催するなど、今後注目のVRプラットフォームです。
VRトラベルAd
VRトラベルAdは旅行者向けのVR動画広告プラットフォームです。株式会社サイバー・コミュニケーションズとナーブ株式会社の共同開発でリリースされました。
ナーブはVRをビジネス活用するというコンセプトのもと、接客にフォーカスしたVR端末「CREWL(クルール)」を開発。VRトラベルAdは、このCREWLを活用し、VR動画を配信することが可能です。例えば旅行代理店で設置されているCREWL上で、VRトラベルAdに登録された観光のVR動画が閲覧可能となります。紙媒体の資料ではなかなか伝わりにくい観光地の魅力も、VRであれば余すところなく伝えることが最大の魅力です。
SNSプラットフォームとして有名なFacebookもVRに注目しており、SEOのザッカーバーグは「次のプラットフォームになるのはVRだと考えている」と発言しています。その裏付けとして、Facebookは2014年にVRゴーグル開発のOculusを買収するなど、VRプラットフォーム実現のために、すでに数十億ドル投資しています。
また、2018年のカンファレンスでもVRに関する発表し、2019年5月には最新のVRヘッドセットの発売を開始するなど、いかに次世代のプラットフォームとしてのVRに可能性を感じていることが伺えます。SNSで巨大なプラットフォームを築きあげたFacebookだけに、VRプラットフォームとしても大きな期待が寄せられます。
まだまだ課題の多いVR広告の今後

VRは依然発展途上に技術であり、まだまだ課題が多いのも事実です。ここではVRに置ける課題を2つと、VR広告についてご紹介します。
VRヘッドセットの流通が少ない
VRという言葉を知っている方は以前に比べると増えたかと思います。しかし、VRを実際に体験したことがある方や、VRヘッドマウントディスプレイを購入したという方はあまり多くありません。また、ヘッドマウントディスプレイの価格が高く、気軽に購入できないという問題もあります。VRの性質上ヘッドマウントディスプレイなどの専用機器がない場合、VRコンテンツを十分に利用することはできません。ヘッドマウントディスプレイの一般家庭への普及が、今後の大きな課題の1つとなるでしょう。
VRコンテンツの作成コストが高い
これまで一般的な動画コンテンツでは平面上のものが多く、一方面から見られることを想定して作成すれば問題ありませんでした。しかし、VRの世界では、360度あらゆる角度を見ることができます。VR世界での没入感を演出するためには、映像やCGに高いクオリティが要求されます。そのため、1つのコンテンツ作成に膨大な時間とコストがかかります。
また、VRコンテンツを作成できるクリエイターが通常の動画に比べて、少ないことも問題視されています。制作できる人材の確保と、制作コストについては今後VRの普及に伴い、解決する必要があるでしょう。
VR広告の今後
ではVR市場は今後どうなっていくのでしょうか?ここで1つ思い出していただきたいのが、スマートフォンです。
10年ほど前、世の中ではガラケーが主流となり、iPhoneをはじめとするスマートフォンはほとんど流通していませんでした。しかし10年後の現在、多くの方はスマートフォンを使用し、ガラケーは街中であまり見かけなくなりました。スマートフォンが利用者にとって魅力的だったため、選ばれたのだと考えられます。
いつの時代も新しい技術は様々な問題があり、どれほど素晴らしい技術も、一般家庭に普及するまで時間がかかります。VRは非日常的な体験や、仮想世界で現実味溢れる体験など、体験した多くのユーザーを魅了しています。シリコンバレーのスタートアップ企業や、GoogleやFacebookをはじめとする大手プラットフォーマーなどが注目している技術でもあるため、今後ますますVR市場は発展していくことが予想されます。VR市場が拡大されることで、広告のあり方も徐々に変化し、VR広告もより一般的なものとなっていくでしょう。
まとめ

今回はVR技術とVR広告についてご紹介しました。まだまだ発展途上のVR技術ですが、今後期待される技術の1つです。
VRを体験したことがない方は、この機会にVR動画を体験してみてはいかがでしょうか?VRの普及に伴い、VR広告もより一層注目を浴びることが予想されます。
今回ご紹介した事例以外にも、様々な企業で実施していますので、この機会に調査してみてはいかがでしょうか。