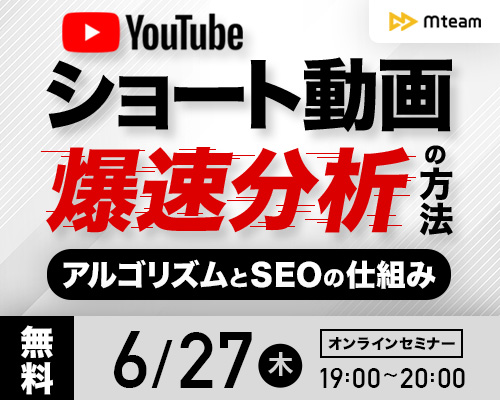コラム

何が違うのライブ配信!通常動画との違いからマーケティングへの活用まで紹介!
目次
ライブ配信とは

ライブ配信の基礎知識から紹介します。
リアルタイムの配信
ライブ配信とは、その名の通り「生」の情報を配信する動画コンテンツです。時間や距離などの制約でその場に行けない人でも、そこで起きていることをリアルタイムで視聴することができます。
新型インフルエンサー「ライバー」
近年話題のYouTuberやTikTokerなどのように、ライブ配信をコミュニケーションツールとして使いこなしている人たちを「ライバー」と言います。このようなインフルエンサーはライブ配信を使ってフォロワーを集め、オンライン上で自身のチャンネルを持ったり、「インフルエンサーマーケティング」などを行ったりしています。
※インフルエンサーマーケティング・・・インフルエンサー(SNSなどで一定数のフォロワーに対し強い影響力を持つ人)に製品などのPRを依頼し購買率を上げるマーケティング手法。
ライブ配信と通常動画の違い

過去に作られた動画コンテンツとは違った臨場感が楽しめるのも、ライブ配信の魅力です。ライブ配信と通常動画の違いをチェックしましょう。
今起きていることを今知ることができる
収録・編集された通常の動画に対し、ライブ動画はその場、その時に起きていることがそのまま配信されます。ユーザーがライブ配信を見る主な目的は、「編集されていないピュアな情報をリアルタイムでキャッチすること」であり、ここが通常動画を見る時の姿勢と異なる点です。
近年、動画コンテンツのマーケティング活用が増加傾向にありますが、ライブ配信は動画の可能性を一層高めるポテンシャルを有しているとして、さまざまな市場で導入が進んでいます。
音楽イベントやスポーツ中継、生番組、製品発表会、株主総会、選挙速報やモデルのオーディションなど…とても広い分野において、ライブ配信の新しい可能性を探る実験が行われています。
インタラクティブ性
ライブ配信と通常動画のもっとも大きな違いは、インタラクティブ(相互的)な体験を提供できるという点で、これはライブ配信が持つ最大の魅力とも言えます。ライブ配信にはコメント機能が設けてあるため、視聴者はコメントを打ち、発信者はそのコメントを読み上げたり、それに応じたアクションを行うことが可能です。この相互性が生み出した、ライブ配信ならではのコンテンツが「雑談」です。
雑談とは、とりとめのない話のこと。動画戦国時代と言われ、動画コンテンツの有益性が重視されている今の流れの中で、雑談は第三者からすると魅力を感じにくいものと言えます。しかし、それがコンテンツとして成立しているのは、ユーザーとライバーが「雑談を楽しむことができる間柄」になっているから。そしてその関係性の構築をアシストしているのが、ライブ配信が持つインタラクティブ性なのです。
ライブ配信を行うメリット・デメリット

通常動画と違い、ライブであるがゆえのメリットもデメリットも存在します。確認していきましょう。
メリット1. 手間とコストを省ける
ライブ配信は、「今」を「ありのまま」に届けることが役目であり魅力でもあるので、当然ながら編集は必要とされません。通常の動画では、良質なものをつくり差別化をはかるためには、高価な撮影機材や編集ソフト、そしてそれらを使いこなす技術や作業の時間など、動画の公開までに多くのリソースが投下されます。
一方、ライブ配信におけるクオリティの主軸は「リアリティ」と「コミュニケーション」なので、前出のようなコストや手間をかけずに質の高いコンテンツを届けることが可能です。
また、講演会やセミナーなどはライブ配信に切り替えることで、講演者や聴講者の移動時間や移動費用、会場をおさえるためのコストなどを大幅に削減することが実現します。また、配信した映像をアーカイブに残せば二次利用もできるため、コストパフォーマンスの良いマーケティング手法とも言えるでしょう。
メリット2. マネタイズの効果促進
ライブ配信プラットフォームは、各プラットフォームによってユーザーの層が異なります。例えば、ニコニコ生放送は男性ユーザーが多いのに対し、ツイキャスは若年層の女性ユーザーがメイン、そしてLINE LIVE CASTは幅広い層によって利用されています。この棲み分けを利用することで、特定のターゲット層に対して深いアプローチを行うことができるでしょう。
また、ライブ配信が持つコミュニケーション機能は、信頼と親近感の獲得に大きく貢献します。親しい人や信頼できる人から紹介された商品は購入率が高い傾向にあるように、ライブ配信での製品紹介には高い訴求効果が期待されます。特に、インフルエンサーマーケティングとライブ配信は相性の良いマーケティング施策の1つと言えるでしょう。
ライブ配信におけるデメリット
ライブ配信のデメリットは、「一発本番」であるという点。配信中に不具合やトラブルなどが起きても編集することができません。
余計なものが映り込まないか、音などの邪魔が入らないか、回線の状況は問題ないかなど、事前にできる準備は入念に行いましょう。加えて、コンプライアンスへの配慮も重要です。また、万が一の場合でも柔軟に対応できるように、幅を持たせたシナリオを準備しておくと安心です。
ライブ配信を行う効果

一言で「ライブ配信」と言っても、掛け合わせるコンテンツによって、そのマーケティング戦略や得られる効果は異なります。ここでは、ライブ配信を活用するマーケット別にその効果を解説します。
イベント×ライブ配信 ー “一度きり”を共有できる特別感
音楽ライブやファッションショーなどには、「その時にしか生まれない空気」があります。ライブ配信では、視聴者が今感じたことをリアルタイムでコメント欄にあげ、他者と感情を共有・増幅させることが実現します。
特に、音楽フェスやハイブランドのランウェイショーなどの話題性のあるイベントでは、その話題がホットであるうちに高揚感をシェアすることに価値が見出されるもの。“一度きり”をリアルタイムで体験したことに熱や優越感を持った人は、それを「早く伝えたい」と思うので、情報は自ずと速いスピードで拡散されることが期待されます。
番組×ライブ配信 ー “一緒に”作り上げる楽しさ
台本と編集によって作り込まれた収録番組と異なり、ライブ配信による番組では、配信者は視聴者のコメントを読みながら番組を進行していきます。また、誰かのコメントに他の視聴者が便乗するなど、横とのつながりを感じることができるのも魅力です。
そのような「参加できる楽しさ」や「交流できる嬉しさ」は、視聴者との距離を縮め、一視聴者をファンやフォロワーに変えることにもつながるでしょう。
講演×ライブ配信 ー コミットメントを高める
学会や講演会の場合は、収録されたものでもライブ配信でも、講演者が話す内容は基本的には同じです。しかしライブ配信を行えば、参加者それぞれが抱いた不明点や疑問点をその場で質問し解消することができるので、学ぶ意欲と理解度をが高めることができます。
SNS×ライブ配信 ー コアなファンをつくる
YoutubeやInstagramは気楽にフォローできるため、比較的フォロワー数を稼ぎやすいSNSとされていますが、熱を持ったファンは獲得しにくいという難点があります。それらのメインコンテンツは動画や写真なので、投稿者とフォロワーのコミュニケーションは、タイムラグのあるLikeボタンと短めのコメントにおさまりがちだからです。
そこを補填する助っ人がライブ配信機能で、仮想のように感じていた互いの存在を近く、現実的に感じることが実現します。これによって、数字だけの1000人ではなく、10人のコアなファンを創出することが可能となるでしょう。
ちなみに、インスタライブやLINEライブはフォロワーや友達のみが視聴できるシステムになっていますが、これを逆手をとっているのがインフルエンサーです。さらなるフォロワー獲得を狙って、あえてそのような制限があるライブ配信を利用するという戦略です。
販売×ライブ配信 ー エンゲージメントを高める
製品の発表や映画の告知など、新しい商品のプロモーションにおいてもライブ配信は効果的です。取り直しのないプレゼンテーションでは、商品開発のバックグラウンドやローンチに向けた想いなど、プレゼンターの熱がそのままユーザーに届きやすく共感を得やすいという効果が期待さえます。また、コメントでの質疑応答によって情報の不足をカバーすることで、商品をより深く知ってもらえるようにもなります。
中国では「ライブコマース」という、ライブ配信とEコマースを掛け合わせたマーケティングが勢いを増しています。形としては、従来のテレビショッピングにインタラクティブ性が加わったもので、新しいEコマースとして注目を集めています。
実況×ライブ配信 ー 臨場感を生む
スポーツやゲームなど興奮やスリルを伴うコンテンツは、臨場感や一体感を体験することが最大の魅力です。ライブ配信では、その魅力を損なうことなくダイレクトに届けることが可能になります。
ライブ配信をマーケティングに活用した事例

それでは、実際にライブ配信をマーケティングに活用した事例を紹介します。
バーバリー
2010年、業界で初めてファッションショーを3Dでライブ配信したことが話題を呼んだバーバリーは、それ以降も意欲的にデジタルマーケティングに取り組んでいます。
例えば2015年、バーバリーはLINEと連携して、とても巧みなマーケティング施策を成功させています。ショーのライブ配信前、その認知度を上げるためにLINEのメッセージ機能を使ったリマインドを行い、バーバリー柄のコートやマフラーをあしらったスタンプの配布を実施。ライブ配信時には8万人を超える視聴者を集客し、さらにライブ直後には、モデル着用商品をすぐに購入できるオンラインサイトへ誘導するという、シームレスなマネタイズフローをつくり上げました。
ライブ配信が生む付加価値を最大の状態で売り上げへとつなげる、お手本的マーケティング事例と言えるでしょう。
インフルエンサー “ゆうこす”
女子の「モテる」をクリエイトする、モテクリエイター「ゆうこす」こと菅本裕子さんは、SNSの総フォロワー数150万人超えを誇る20代インフルエンサーです。10代〜20代前半の女子を中心に高い支持を得ています。
そんなゆうこすさんは、「インフルエンサーマーケティング」の一つである「ライブコマース」でも高いエンゲージメントを獲得しており、「ライブコマースの第一人者」と言われるほどの実績をあげています。
注目すべきは、ファンを開発段階から巻き込む「共創マーケティング」という手法です。商品を説明して販売する、という一般的なライブコマースのアプローチではなく、ライブ配信を「女の子のリアルな要望を聞き取る場」とし、皆で話し合いながら商品を開発・販売するというマネタイズを行っています。モノが溢れる現代では、商品の力だけで差を生むことは困難とし、そこに「ストーリー」を加えることで商品への思い入れを高めようという戦略です。
ライブ配信のコメント機能を生かし、「相手の声に耳を傾ける」という姿勢に重きを置くことで信頼と好感を得たマーケティング例です。
グリー株式会社
SNS「GREE」を提供するインターネット企業グリー株式会社は、株主総会プロセスのIT化に着目し、2019年に国内で初めての「ハイブリッド型バーチャル株主総会」を実施しました。
現行の株主総会は、「一部の株主しか参加できない」という課題を抱えています。理由は、時間や会場のキャパシティーなどによる制約です。経済産業省は、株主総会の対話環境を整備すべきと考え、2020年2月に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しています。
このガイドラインでは、「ハイブリッド型バーチャル株主総会」を以下のように定義しています。
“取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。”
※引用:経済産業省「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」
実際にグリー株式会社が実施したバーチャル株主総会では、株主の層が多様化したことによる新しい対話が生まれ、株主側からも高い評価が得られたようです。バーチャル株主総会はまだ事例はほとんどなく、セキュリティー面やITリテラシーのギャップなど手探りの状態ではありますが、業界から高い関心を集めているライブ配信事例です。
ディズニー
2016年、アメリカのウォルト・ディズニー・カンパニーは当時の最新作、「ジャングルブック」のワールドプレミアをFacebookライブで生配信する、というプロモーションを行い話題を集めました。
このライブ配信に向けてディズニーがタッグを組んだのは、宿泊施設のレンタル仲介サービス大手 Airbnb。映画の舞台となるジャングルの世界観を表現するため、世界中のユニークな宿を仲介しているAirbnbが、会場としてツリーハウスを提供しました。
このように作り込まれた世界観や、ドレスアップしたセレブリティーがインタビューに応じる様子など、非日常の世界を身近に感じるという貴重な体験が大きな反響を呼び、アーカイブ動画は10万回近くまで再生されました。
ライブ配信ができるサービスを紹介

ライブ配信に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。ここでは、ライブ配信ができるサービスを紹介します。
ライブ配信のプラットフォーム
ライブ配信市場の成長によって、数々のプラットフォームが生み出されました。代表的なライブ配信プラットフォームとして、以下のようなものが挙げられます。
- TwitCasting(ツイットキャスティング。通称:ツイキャス)
- SHOWROOM
- 17 Live(イチナナライブ)
- MixChannel
- ニコニコ生放送
- Pococha(ポコチャ)
- LiveMe
上記のサービスは全て、パソコンとアプリの両方から配信することができます。
SNSのライブ配信機能
画像や動画、テキストなどをメインコンテンツとしているSNSも、ライブ配信機能を強化しています。
- LINE: LINE LIVE CAST
- YouTube:YouTube Live
- Facebook:Facebookライブ
- Instagram:インスタライブ
- twitter:Periscope(ペリスコープ。twitterが開発したライブ配信アプリ)
企業向けの動画配信システム
企業が会議やセミナーをライブ配信する際は、セキュリティやアクセス管理などを厳格化する必要があるため、法人向けの有料配信サービスを利用することをおすすめします。
- millvi(モバイル機器にも対応)
- Video Marketing Suite(モバイル機器にも対応)
- 3eLive
- viaPlatz(ビアプラッツ)
- クラストリーム
- necfru Media Cloud(モバイル機器にも対応)
- ULIZA(モバイル機器にも対応)
- J-Stream Equipmedia(モバイル機器にも対応)
まとめ

活況にある動画マーケティングは、5Gの導入によってさらに発展することが予測されます。ライブ配信については継続的にその動向を調査し、時代に合ったマーケティングへの活用方法を探ると良いでしょう。
WEBでのお問い合わせはこちら