コラム
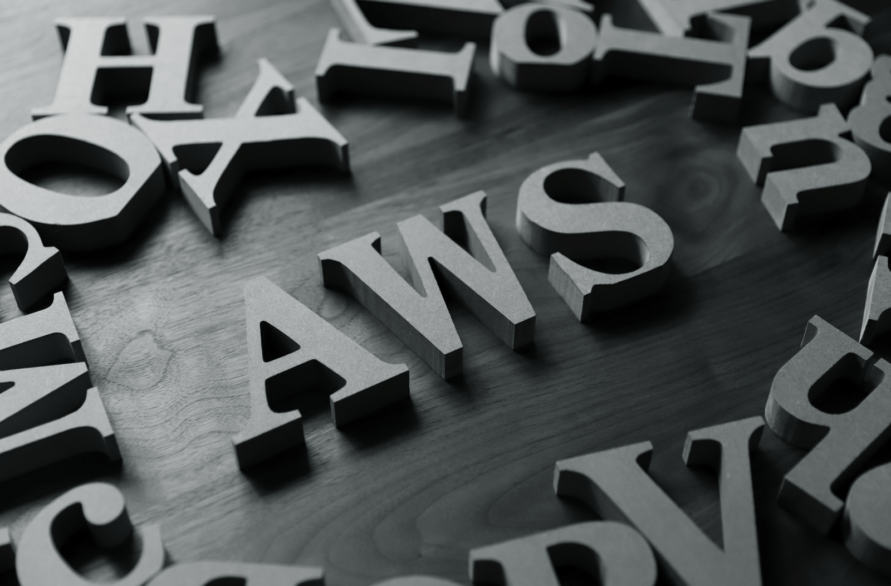
【今さら聞けない】AWSとは?基礎から徹底解説します!
最近はアルファベット3文字のサービスやビジネス用語が多く、何がなんやらとなってしまいがちで、AWSと言われても聞いたことがあるような気もするので、知ったかぶりをしてしまったりするかもしれませんね。今回はそのAWS(アマゾンウェブサービス)について、初めて知る人でもわかるように解説をしていきます。
目次
AWS(アマゾン ウェブ サービス)とは?何がすごいの?

AWS(アマゾンウェブサービス)とは、Amazonが提供しているクラウドコンピューティングサービスです。
これの何が凄いのかを初めに簡単に説明すると、アマゾンが提供する175以上のサービスを低コストで利用できてしまうのです。代表定期なところでお伝えすると、サーバー構築やデータ保存環境構築・セキュリティ環境など自社で全て賄うと手間とコストがかかることを、AWS上でまとめて行うことができるのです。
そもそもクラウドサービスとは?
そもそもクラウドサービスとは何なのでしょうか?正しくはクラウドコンピューティングと呼ばれており、簡単に言えばインターネットを通してPCに必要な機能を間借りすることなのです。
例えば、身近でよく使われるのが、写真や動画の保存です。自分のPCに動画を保存したくても容量が足りないとします。そのときにクラウドサービスを利用して、外部ストレージに自分の動画を保存することができるのです。
その他にも例えばエクセルのように、通常ソフトをインストールしなければならないソフトウェアを、インストールせずにインターネット上で使うこともできるのです。
クラウドサービスのメリットは?
クラウドサービスを利用する主なメリットは以下のようになっています。
- 設備投資のコストを抑えられる
- ソフトウェアの更新などメンテナンスが不要
- インターネットを通じて使うのでどこでも情報共有ができる
- システムの拡張性が高い
クラウドサービスには様々なメリットがありますが、特にシステムに対する初期投資のコストを抑えられる部分が大きいです。
また、機能も多くあり、わずかな時間で新しい機能の導入やシステムを構築することができるので、人件費や外注費の削減にもつながります。そして、その時々に合わせて必要な機能を利用すれば良いので不要な機能に余計なコストをかける必要もありません。
AWSのクラウドサービスは何がすごいの?
では様々あるクラウドサービスの中でAWSは何がすごいのでしょうか。AWSの凄いところは、Amazonを運営するにあたり蓄積したインフラや機能をクラウドサービスとして一般の人が使えるようにしてしまっている点なのです。つまり、巨大企業が計り知れないほど投資をして作ったシステムを、レンタル料を払うだけで使えちゃうということですね。
具体的には以下のようなポイントがあります。
- 小規模から大企業まで使える機能の柔軟性と拡張性がある
- 一般的なクラウドサービスに加え、ビジネスに必要なツールが揃っている
- 機械学習や人工知能など最新の技術もある
- 世界レベルの高いセキュリティと安定したパフォーマンス力がある
AWSには175以上のサービスがあります。もちろん全てを使うことは難しいですが、小規模企業から大規模企業まで使える高機能ツールがたくさんあるのです。新しいツールを外部から導入することは時間もお金もかかります。企業の成長に合わせてAWS上で機能を拡張できるのは大きなメリットですよね。
AWSの種類

AWSには様々な種類のサービスがありますが、その種類が多すぎて一体何を使えば良いのかわからなくなりがちです。ですがこれらは一度に覚える必要はありません。ここでは具体的に、AWSの中でよく利用されるサービスとその機能をお伝えしていきます。
AWSで主によく使われているサービスの種類は以下の通りです。
- Amazon EC2
- Amazon S3
- Amazon EBS
- Amazon RDS
ではそれぞれ見ていきましょう。
Amazon EC2
EC2とはElastic Compute Cloudの略でAWS上で「仮想サーバー」を作ることができるサービスです。通常サーバーをレンタルしたり購入をすると、手間のかかるネットワーク構築作業が必要でした。また、長年使っているとメモリが足りなくなったりして、増強するのにこれも手間がかかっていました。
EC2ではLinuxやWindowsOSをそのまま利用して簡単にシステム構築ができます。また、メモリが必要になった場合はEC2上ですぐにメモリ増設ができるようになっています。
複数の仮想サーバーを立てることができるので、本番用と検証用サーバーとで使い分けをするなども可能です。これは基本機能になるので他のAWSサービスを使って機能を追加していく形になります。
Amazon S3
S3とはSimple Storage Serviceの略で、データの保存サービスです。ウェブサイトやアプリケーションの保管、バックアップデータやIoTデバイスの保護まで様々なデータの保管をすることができます。
クラウド上にデーターを保管することに抵抗がある方がいるかもしれませんが、 S3では暗号化機能とアクセス管理ツールを用いることで不正アクセスなどからデータを保護することができます。コストパフォーマンスも高く、データの上限がほぼないので大企業でも利用されています。
Amazon EBS
EBSとはElastic Block Storeの略でE2Cと併せて利用するブロックストレージサービスです。E2Cは仮想サーバの役割になり、EBSはそれにつながるデータを呼び出したり書き込んだりするHDDの役割になります。
利用状況に応じてボリュームを調整できるので、必要に応じた利用ができ、コストパフォーマンスに優れています。このEBSは保存しているデータをバックアップして複製や切り離すこともできるので、E2Cで構築した他の仮想サーバーに取り繋ぐことも可能です。
Amazon RDS
RDSはRelational Database Serviceの略で、様々なデータを整理して管理ができます。データの管理を各々で行うと情報の更新や共有が正確にできなかったりしますよね。また、保管リスクも出てきます。
RDSではこれらのデータを保管するデータベースをクラウド上にセットアップとオペレーション環境を構築することができます。そして必要に応じてスケールを簡単にすることができます。
パッチ適応やバックアップも自動で行えるため手間もかかりません。Amazon RDSは環境に最適なデータベースインスタントタイプを選択でき、使い慣れたデータベースエンジンを利用することができます。Database Migration Serviceを利用すれば既存のデータベースを移行することも可能です。
AWSの主な機能

ではここからは、AWSのサービスで使える機能をお伝えしていきます。
- 分析
- アプリケーション統合
- AWSコスト管理
- ブロックチェーン
- ビジネスアプリケーション
- コンピューティング
- コンテナ
- カスタマーエンゲージメント
- データベース
- デベロッパー用ツール
- エンドユーザーコンピューティング
- ウェブとモバイルのフロントエンド
- Game Tech
- IoT
- 機械学習
- マネジメントとガバナンス
- メディアサービス
- 移行と転送
- ネットワーキングとコンテンツ配信
- 量子テクノロジー
- ロボット工学
- 人工衛星
- セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス
- サーバーレス
- ストレージ
- VRおよびAR
これらの種類は全部覚える必要はない
結論から言うとこれらの機能は全部覚える必要はありません。なぜならこの中から、必要な機能を有し一般的に使われるサービスはある程度限られているからです。そして、これらの種類の中からさらに用途に合わせたツールで分かれているので覚えるのも大変なのです。
まずは、自分たちが普段利用している既存のシステムを利用するにあたって必要な機能を調べましょう。そして追加で必要な機能を選ぶことをおすすめします。
AWSは全部最初から構築しないといけないの?既存のシステムは移行できる?
自社のシステムやデータベース・サーバーなどをAWSでは移行をすることが可能です。そして移行したシステムとAWSの機能を連携させて利用することもできるのです。既存システムの移行をすることができるので、AWSで全部最初からシステムを構築する必要はないのです。そして既存のシステムを利用して、分析ツールや人工知能ツールを取り入れて進化させることも可能です。
AWSにかかるコスト

ここまでお伝えしたように、これだけ高機能で高品質のサービスを提供しているAWSのコストはどれくらいかかるのでしょうか?ここではAWSの料金体系に関してお話ししていきます。
AWSの料金体系の特徴は従量課金制になっていることです。従量課金制とは、必要なサービスを使った分だけの料金を支払うと言うことです。サービスの種類によって異なりますが、1時間あたりの使用料金と利用容量で計算されます。サブスクリプションのように毎月固定型の料金になるわけではありません。そのためAWSを解約したときの違約金なども無いのです。
使うサービスによって料金が異なる
AWSは必要な機能に必要な分だけ課金する形式になっています。そのため使うサービスによって料金が異なってきます。データの使用容量や利用時間によって異なるため、24時間稼働が必要ではないシステムや通信容量が少ない場合は費用は少なく済みます。
料金の見積もりをしたい方はこちらを利用してみて下さい。
従量課金制のメリットとデメリット
従量課金制にはメリットとデメリットがあります。
メリットは
- 使った分だけの利用なので、使用する機能が限定されればコストが安く済む
- 長期的に使うかわからない機能を試しに使ってみることができる
- 変化に柔軟に対応できる
一方でデメリットは
- 料金の変動が出るので予算が組みにくい
- 使いすぎると予算が超過する可能性がある
このようなメリットデメリットがあります。デメリットもありますが、必要な時に必要な分だけ使える点においてはメリットが大きいですよね。
特定の機能を長期的に使うのであれば節約ができる
AWSは従量課金制ですが、以下のサービスにおいては1年や3年の契約をすることで経費を削減することができます。
- E2Cリザーブドインスタンス
- RDSリザーブドインスタンス
- リザーブドインスタンスマーケットプレイス
こちらは1年分のデータ容量や利用時間を事前予約をして支払うことで、30%〜最大72%の割引を受けることができます。AWSを基本的に利用することが決まっているようであればこちらを利用しても良いでしょう。
AWS導入の難易度は高い?

AWS導入は素人でもできるかどうかというと正直難しいです。自社で自力でAWSを導入してサーバー構築をすることは難しいでしょう。
基本的にAWSは、エンジニアがインフラ構築やサーバー周りの構築をしていく機能になります。素人でも利用できるクラウドストレージとは全く別物になっています。そのため、AWSを導入できるスキルを持ったエンジニアが基本的には必要になります。AWS検定があったり、AWSを専門としたエンジニアがいるくらいのスキルが必要な分野なのです。
エンジニアがいてもAWS導入は難しいのか
では自社にインフラエンジニアがいる場合はどうなのでしょうか。その場合でも、導入にはサーバー構築やクラウドに関する知識がある事が前提です。そうした知識を有していない場合には、自社エンジニアがいる場合でもAWS導入の支援をもらったり、AWSに関するトレーニングをする必要があるでしょう。
AWSの公式サイトではトレーニングと認定を受けることも可能です。
AWS トレーニングと認定
AWSを導入するときの準備は必要
AWSを導入するには相応の準備が必要になります。先ほどもお伝えした通り、導入の難易度はやや高く、知識がある人間が必要になります。そして導入をするにあたり事前の準備も必要です。簡単にAWSを検討するときのフローを紹介します。
- 導入の目的と期間を明確にする
- 技術的観点とビジネス的観点から導入検討をする
- 既存システムや情報の棚卸しをする
- AWSで必要な機能を選定する
- 安全に移行する手順を考えて導入をする
- 運用を始め、最適化を進めていく
ざっくりですがこれらの準備が必要になります。特に初めの企画と準備段階でしっかりと要件定義をしていく必要があるので、そこでの擦り合わせが重要になります。ただ、導入自体は外注をすることも可能です。
導入後の利用や保守運用は難しいのか
AWSは一度導入をして移行が完了すれば、単純に引っ越しをしたようなもので、既存のシステムは再構築することなく通常通り使う事ができるはずです。
また、AWSの機能に関する保守運用はAWS側がやってくれます。常に最新のもので安全に利用ができるので、保守運用コストもかかりません。種類のところで紹介したRDSはデータのバックアップやセキュリティの修正などもしてくれます。
Iotや機械学習ツールは常に変化していくので、自社で全て更新をするのは難しいですよね。AWSの機能をうまく活用をすれば、導入後の保守運用も楽になります。
まとめ:AWSはAmazonが蓄積した技術を共有できる便利なツール

AWSは簡単に言ってしまうと既存のクラウドコンピューティングの機能に加えて、Amazonがこれまで蓄積したツールを使いたい部分だけ使えてしまうツールなのです。
最後にこの記事をまとめると
AWSは世界中の企業で利用されている高機能なクラウドコンピューティングサービスである
その機能は175以上あり、機械学習や人工知能などAmazonが蓄積した技術を利用することができる
AWS導入は簡単ではないので、導入までの入念な準備やエンジニアのスキル取得も必要
AWSを利用すれば、基本的にビジネスシーンで必要なコンピュータ資源を賄うことができます。利用の仕方次第では、自社で開発や構築をするよりもはるかに安いコストでAmazonの高機能で信頼ができるシステムを利用することができます。今回の記事を参考に、ぜひ導入を検討してはいかがでしょうか。
WEBでのお問い合わせはこちら






